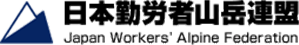Q&A
A1.
日本勤労者山岳連盟(労山)が、遭難対策事業の一環として設定している労山会員のための互助制度です。労山会員が、会員の遭難事故対策のためにお金を出し合って「基金」をつくり、事故を起こした会員の救助・捜索や入通院にかかった費用などが、基金に登録した口数に応じて交付されます。
この制度は、労山の遭難に対する自衛措置としての運営であり、営利を目的としていません。運営は、全国連盟理事会が選出して総会で承認を受けた運営委員で構成される「労山基金運営委員会」が行います。
(規定第1章総則 第1条目的)
A2.
基金には二つ種類「個人」と「団体」があります。
「個人」は加盟団体のすべての会員を対象としています。[ 払込・交付] 方式で、個人ごとの登録口数に応じて救助・捜索に要した費用や、入通院の日数に応じた費用などが交付される制度です。
A3.
団体へは、所属会・クラブが登録することができます。
登録は年間1口2,000円で、1口~ 5口までできます。
国内の事故のみを対象とし海外の事故は適用されません。
救助捜索に要した交付の資格は労山会員に限られますが、交付申請の手続きは団体が行なうので、(当該事故者ではなくて)団体名義の口座に振り込まれます。
ただし、救助・捜索のみが交付対象で傷害の入通院には適用されません。
A4.
労山の会員であれば、誰でも、いつでも登録できます。登録手続きは、所属団体(会・クラブ)の労山基金の担当者が、労山基金運営委員会宛てに所定の書類を提出して申請します。交付などの諸手続きも、会員の所属する会・クラブと運営委員会とで行われます。
(規定第1章総則 第3条運営)
A5.
1年単位で、個人加入の場合は1口1,000円で、任意の口数で寄付金を登録できます。
目安として基金運営委員会は、ハイキング・軽登山は3口以上、雪・岩・沢で5口以上を、冬期登攀・海外登山などには10口を、と呼び掛けています。
A6.
基金の登録は、所属団体(会・クラブ)、地方連盟、地方協議会などごとに期限が統一されています。例えば、期限月が5月となっている場合、その団体の登録期間は、6月1日から翌年5月31日までです。
(規定第5章基金 第15条登録期間 細則ー4登録期限月の統一)
A7.
期限月の2ヶ月前(例えば5月が期限月の会であれば3月31日頃)に基金運営委員会から「継続申込書」が担当者に送付されます。
その「継続申込書」に申込口数と金額を記入し、運営委員会へFAX または郵送にてお送りください(Eメールでの送信の場合、PDFファイル のみ受理します)。期限月の末日までにこの手続きができていなければ、労山基金の継続が切れます。
寄付金は登録期間終了後、運営委員会から送付される「精算書」に基づき、同封された「払込取扱票」(赤)で郵便局から送金します。
A8.
<団体加入の場合> 新規に申し込みする場合は、登録する月から所属会・クラブの期限月までを、寄付金口数X2000円、途中加入の月割り計算はありません。
<個人加入の場合> 新規に申し込みする場合は、登録する月から所属会・クラブの期限月までを、残り月数X1口100円として月割計算します。
例えば、5月の期限月の会・クラブが、11月から登録する場合は11月(月内の日割り計算はしない)から翌年5月までの7ヶ月分となります。
100円×口数×7ヶ月です。 その有効期間は5月末日までです。
6月1日からは、1年分を1口1000円で計算して継続します。
期限途中で口数を増し口(追加)する場合は、期限月までの残りの期間の長短にかかわらず1口1000円で、月割り計算にはなりません。
増し口の登録期間は、期限月までです。
「新規登録申込書」「増し口(追加)申込書」はサンプルを担当者に送付してあります。
送付は、FAX、郵送、Eメール添付のいずれでも結構です。
A9.
有効期間の中途で退会したとしても、月割り計算はおこないません。申し込みされた1年分の額で(有効期間終了後)精算します。
労山基金は「寄付金納付・交付」方式の制度です(規程第16条)。
労山基金はサービスの有効期間終了後に寄付金を納入する「後払い制度」となっています。寄付金の性格と後払い制度の設計から返金の扱いは考慮していません。
A10.
新規登録の場合は、所定の手続きを行い、申し込みを運営委員会で受理した日から登録が有効です(土日祝除く)。
有効期限内に継続申し込みが行われれば、次年度に登録が更新されます。登録が完了する前に有効期限が切れた場合は、新規と同様に受理日からの登録となります。
A11.
入通院についての交付金は、事故の日の登録口数で決まります。
救助・捜索費の実費補填については、交付限度額の倍率が登録年数を重ねるごとに大きくなっていきます。登録初年度は、払込金の400倍ですが、継続2年目は410倍、3年目が420倍と言うように10倍ずつ最高500倍まで加算されます。
但し、国内のみが対象で海外の場合は400倍となります。
交付倍率が加算されるためには、登録の継続が必要です。継続が切れてから、再登録したときは新規登録1年目となって倍率の加算が適用されません。このため、運営委員会は、期限を過ぎても1ヶ月間は猶予する救済期間を設けています。
5月期限月の場合は6月末日までに手続きすれば、継続は切れません。ただし、これは倍率加算の特例措置であって、期限月を過ぎると継続手続きをするまでは、労山基金は未登録です。その間に事故が発生しても交付は受けられません。
A12.
通院400円です)入院は2日以上継続した場合、および通院は1日目から交付対象になります。
登録1年目は払込金の400 倍が限度額です。2年目で410倍、3年目で420倍というように10倍ずつ加算されます。
A13.
登録口数は、ご自身の山行形態や他の山岳保険などへの登録の有無などからお決め頂くことになります。
「救助・捜索費用は幾ら掛かるの?」(後述)を参考にして下さい。
運営委員会では、ハイキング・軽登山の山行形態に3口以上、雪・岩・沢で5口以上を、冬季登攀・海外登山などには10口を、と呼びかけています。
A14.
海外の山行で労山基金の交付を受けようとする場合は、所属会への山行計画書の提出という国内山行での通常の手続きに加えて、事前に全国連盟海外委員会へ計画書の提出が必要です。個人加入の交付内容は、救助・捜索は加入継続年数にかかわらず400倍とし、死亡・傷害は国内山行と同様です。
なお、トレッキングとは異なる5,000メートル以上の高所登山および、すべてのバリエーション登山等*については、基金加入してから1年以上経過した会員のみに対して有効です。
(規定細則2山行規定より)
*補足 バリエーション登山とは、ピッケル、アイゼン、ロープなどの登山用具を利用しての登山をいう。
「海外登山届」の送付先はこちらです
A15.
労山基金の交付を受けるためには、事故日から30日以内に事故発生の連絡(事故一報)を運営委員会に行う必要があります。事故一報は所定の書式を使用し、郵便、FAX、Eメールのいずれかでお送りください。書式は会・クラブの基金担当者へお送りしていますし、労山HPにも掲載しています。http://www.jwaf.jp/fund/procedure/index.html
事故一報が事故日から30日を過ぎると、交付認定から除外されます。事故後すぐに症状が現れていなくても、また交付の申請をするかどうか判然としない時でも、事故発生の報告をしましょう。
(規定第5章基金第17条交付申請)
A16.
事故発生後、30日以内に運営委員会が事故一報と山行計画書を受理したら、交付申請に必要な書類が送られます。事故一報は労山で定めた用紙です。山行計画書は事前に所属団体に提出した計画書のコピーです。交付申請期限の、事故日から1年以内に申請を行って下さい。
申請に必要な書類は、交付申請書(委員会より送付の書面に記載、地方連盟代表者の確認を要する)、入通院証明書(入通院の場合)、救助・捜索費用の領収書及び明細書(救助費用が掛かっている場合)、新聞などに報道された場合は、そのコピー、人工壁事故確認書(人工壁での事故の場合)(規定第5章基金第22条交付申請の期限)
A16-B.
各種書類は、郵便・FAX・Eメールのいずれかで送付してください。
○ 事故の連絡は、事故一報のフォーマットを添付ファイルで受理しています。
○ 新規登録・追加(増し口)は、所定のフォーマットを添付ファイルで受理しています。
○ 継続申込は、所定の「有効期限通知・継続申込一覧」をPDFファイルでのみ受け付けております。
PDF以外は、FAXか郵便でお送り下さい。
○ 払い込みには、ゆうちょ銀行インターネットサービスが利用できます。郵便局の窓口では払込料金加入者負担の赤い払込取扱表を使いますが、インターネットを利用したゆうちょ銀行同士の振替送金も、月5回までは無料になります。
送金先への通知には送金元の口座名が表記されますので、利用するインターネットサービスの口座が登録団体名義であればそのままでかまいませんが、個人名義の場合は、通信欄に「地方連盟・所属団体名・担当者名」の表記が必要です。通信欄を利用する場合は有料(100円)です。
A17.
交付の対象となる日数は、入院が2日から210日、通院が1日から50日で、対象期間は、入通院いずれも事故日から一年以内です。
入通院証明書などの文書代金は、交付の対象ではありません。
証明書類の作成にあたっては、下記のうちいずれか一つの方法を選んでください。
(1)運営委員会が送付した「入通院証明書」に医療機関で記載してもらう。
(2)運営委員会送付の「入通院証明書」を事故者自身で記載し、入通院日数を証明できる書類(日付・医療機関名等の記載されている領収書など。コピーは不可)を添付する。添付領収書の返却を希望する場合は、返却希望と明記し返信用封筒(〒、住所、氏名、切手貼付)を同封して下さい。運営委員会で確認後、返却いたします。
(3)運営委員会送付の「入通院証明書」を事故者自身で記載し、他の保険会社仕様の入通院日数を証明できる書類(コピーは不可)を添付する。
この場合も、添付書類の返却を希望する場合は、返却希望と明記し返信用封筒(〒、住所、氏名、切手貼付)を同封して下さい。 運営委員会で確認後、返却いたします。
(規定第5章基金)
A18.
遭難が発生して、迅速な救助や捜索を行うためには、山域の地元遭対協の方々に出動していただくケースが多くなります。また、ヘリコプターによる搬出が必要な場合も少なくありません。
警察や消防・防災のヘリコプターが稼動できない場合には、民間のヘリ会社に出動してもらうことになり、当然、その運賃は事故者の負担になります。
例えば、長野県諏訪地区の遭対協では、隊員の謝礼が季節によって3万円から5万円、保険料の遭難者負担2万円(それぞれ1人1日、保険料は遭対協の負担分もある)、隊長・班長手当などの規定があります。
ヘリコプターの費用は、遭難者救助に最も活躍している東邦航空では、1時間当たりで、空輸料が約47 万円、サーチ・レスキュー料が約51万円です。
冬の八ヶ岳広河原沢で転落骨折した事故の事例では、遭難場所の地形が困難な氷瀑というということもあって、東京からヘリを回送する料金も含めて遭対協と合わせた費用は260万円余りでした。西穂高での転落死亡事故では、ヘリによる遺体搬出を含めて約140万円がかかっています。
ヘリコプターの料金は別にしても、遭対協から請求される救助出動の費用は、全国一律というわけではなく、地方によってかなり大きなバラツキがあります。
A19.
○出動の実費、消耗品の補てん費用
(1)救助・捜索に要したヘリコプターのチャーター料金(民間)
(2)地元山岳遭難防止対策協会(遭対協)などから請求のあった出動費用(民間)
(3)当該会を含め労山の救助・捜索隊出動に要した実費(交通費・食費など)
(4)他パーティーから拝借した装備が損傷し、弁済したザイルなどの消耗品。労山救助隊の出動で損傷した装備の補てん費用。ただし、事故の当該パーティーの装備の損傷は、対象外。
(5)救助捜索費用として認められないのは、ほかに遺体の搬送費用、事故者家族の駆けつけ費用(注)がある。
(注)細則-9 [救援者費用]では、遭難者の安否確認や身柄の保護のために、当該団体が現地に要員を派遣する必要が生じた場合、交通費の実費について10万円を限度として交付する制度を設けている。ただし、救助捜索費を申請する場合は、この者が救助捜索に加わった場合に交付する。
○救助隊の日当
(1)地元遭対協から請求があった日当。
(2)労山地方連盟救助隊の日当。
交付対象は、当該会の代表者が出動を要請して、救助隊から請求のあった費用。費用の算出は、これまでの交付実績をふまえ、夏季10000円、冬季15000円を上限とします。
(3)当該会の救助隊員は地方連盟に救助隊員として登録したものに限ります。
A20.
救助・捜索費の交付申請には、費用の領収書(コピー不可)と明細を添付して下さい。領収書を発行できない性格のものは、領収書なしと記載の上、明細書のーが出動し、大きな金額の支払いが生じた場合は、請求書での仮交付申請も可能です。
(規定第5章基金)
A21.
多額の請求や支払いがあり、交付申請をするまで日時を要する場合には、仮交付申請が可能です。委員会にご連絡ください。
仮交付には、仮交付申請と所属団体へ事前提出された山行計画書の写しが必要です。仮交付は、死亡交付金は全額、救助・捜索費用は、出費の確定している費用で、交付率の限度枠以内であり、救助・捜索費用として妥当と認められる範囲の金額になります。
(規定第6章仮交付)
A22.
次の条件を満たす山行は、定められた交付率の3倍まで交付されます。
ただし、通常交付の10口分までを交付の上限とします。
(1)岩、沢、雪、海外を除く。
(2)標高2,000m以下
(3)標準コースタイム5時間以内
(4)日帰り
(5)既設登山道
(規定細則-3 交付の特典)
*当該山行がこれにあたるかどうかは委員会が認定します。
*交付の特典の申請には、申請者からの認定条件を満たしている
ことの提示が必要となります。
*上記項目を満たす山行計画書やガイドブックなどの写しを添付して下さい。
*2000m以下で事故が起きても、計画書での最高到達点が2000mを
超えていれば認められません。
*自分たちの計画書の行動予定時間が5.0時間以内でも昭文社の地図、
自治体が作成したハイキングマップ、出版されたハイキング本の地図上の
コースタイムが5時間以上であれば認められません。
A23.
交付の特典が認定されると、寄付金2口は6口、3口では9口の交付になります。しかし、本来の趣旨はハイキング・軽登山での3口以下を前提にした交付の特典でしたが、5口以上での特典申請が増えてきました。そのため交付の上限を本来の加入口数の3倍とし、かつ、それが10口を超えない内容にしたものです。例えば、4口は3倍すると12口ですが、上限を超えるので10口になります。以降、5口以上加入の申請についても10口になります。
A24.
労山基金は、登録期限が切れていなければ労山内のどこの会に所属が移っても有効です。移籍しても労山基金は新規扱いにはならず、登録継続年数も有効です。
会員が移籍してきたら、移籍先の会・クラブが運営委員会に報告します。
移籍元と移籍先の有効期限月が異なる場合は、移籍元の有効期限月の翌月から移籍先の期限月までの差額を、1口1ヶ月100円で月割計算して、加算または差し引いて払い込んで下さい。
(規定第5章基金 第15条登録期間)
A24-B.
①労山基金の登録を二つの会にしている場合(両会で基金加入に納めている)、
山行に参加する会に計画書を提出してください。
②労山基金の登録がどちらか一方だけの場合、例えばA会だけに基金の登録を
していてA会での山行に参加する場合はA会へ山行計画書を提出します。
一方のB会で参加する場合は、A会とB会の両方に提出する必要があります。
③事故一報の届けは、
上記①の場合はA山行を行った会だけでよい、
②のB会参加の場合はB会のほかA会にも届けます。
以上のことは、原則として労山基金の交付申請の手続きは、
加入者の所属する団体代表者でなければならないからです。
A25.
会・クラブや地方連盟などが主催する「公開の行事や公開山行」で、会員外の第三者が死亡や傷病などの事故にあった場合(行方不明も含む)に適用されます。交付に必要な要件は、(1)責任者(リーダー)が労山基金第二種個人の登録者、(2)会・クラブや地方連盟などが主催する公開の行事や公開山行、(3)事故者が会員外の第三者、(4)交通機関の事故は対象とはしない、(5)交付金は当該の申請した団体の代表者に支払う。
交付金額は(1)死亡・行方不明、重度の後遺障害を残す傷病に30万円、(2) 2日以上の入院または20日以上通院の重度の傷病に10万円、(3)2日以上20日未満の軽度の傷病に3万円。
(規定細則ー6 付加見舞金制度)
A26.
労山基金の第二種基金個人の登録者が、遭難事故の捜索・救助活動中、二重遭難した場合には、定められている交付率の5倍で交付されます。
(規定細則5二重遭難見舞制度)
A27.
遭難対策事業の一環として設定された労山基金の役割には、事前の事故防止と対策の促進、事後の経済的負担の軽減があります。
その事前の事故防止活動や教育研究活動のために「安全対策基金」を設け、労山基金から資金を提供する制度が1988年につくられました。現在は基金払込金の20%(上限1,500万円)が「安全対策基金」に提供されています。
安全対策基金は、全国連盟理事会の管理の下で、中央登山学校や地方講習会、救助隊や遭難対策関係への活用、地方協議会と地方連盟登山学校への補助などに利用されています。
(規定第4章財政第11条)
A28.
いずれも所属団体(会・クラブ)の代表者です。
所属団体の代表者が申請し、所属団体名義の口座に交付金が払い込まれます。
(規定第5章基金 第17条交付申請 第21条交付金の受領者)
A29.
次の場合には交付されません。
(1)無届山行(所属会・クラブに山行計画書が事前に提出されていない)。
(2)事故日から30日以内に、運営委員会へ事故発生の連絡(事故一報)がない。
(3)事故日から1年以内に交付申請がない。
(4)海外登山・トレッキングの場合に、全国連盟海外委員会に事前の山行計画の提出がない。
(5)交通事故及び交通機関の事故。
(6)委員会が交付対象外と判断したもの。
(規定第5章基金 第18条認定 細則ー2山行規定)
A30.
交付申請ができるのは1年間に2回までです。3回目は対象になりません。1年は、所属団体の期限月の翌月1日を起点として、例えば5月が期限月であれば、6月1日から翌年5月31日までになります。この期間に起きた事故のうち、交付回数のことを指します。
(規定第5章基金 第20条5項交付の対象と算出方法)
A31.
事故日より1年です。1年を過ぎると失効します。特別の事情がある場合は、1年以内に運営委員会へご連絡下さい。
(規定第5章基金 第22条交付申請の期限)
A32.
ゲレンデスキー場でのスキーの事故は労山基金の対象ではありません。但し、
(1)山スキーの下山でスキー場を通過中の事故、
(2)山スキーの練習を会主催で行うゲレンデスキー場での事故、
(3)山スキーの装備で山スキーのトレーニング中は対象とします。
いずれも事前の山行管理が必要で、申請には山行計画書の写しが必要です。
A33.
トレイルランの競技大会に参加する場合は、登山とは違うジャンルだと線引きしていますので、ゲレンデスキー、ケービング、マウンテンバイク、パラグライダー、ウォーキング(個人企画)などとともに、交付の対象から除外しています。
但し、競技ではない形で、会の山行管理の手続きに沿ってトレイルランを楽しむ場合には交付対象として救済しています。
トレイルラン競技では、「ハセツネCUP」などが知られていますが、そのホームページを読むと、「山岳遭難対策制度」に加入していることが参加資格の1つになっています。この点について当委員会がハセツネCUP主催者に見解を確認したところ、山岳遭難対策制度への加入を参加条件にするのは、「練習中や試走時にも同じように遭難の恐れがあるため普段から遭難対策をして欲しい」という趣旨なので、労山基金は参加資格の条件を十分に満たしているとのことです。また、競技中の事故については、エントリー条件の範囲で主催者が掛ける保険で対応するそうです。
トレイルラン競技の参加条件や事故対応は主催者によってさまざまなので、よく確認したうえで参加して下さい
A34.
人工壁での事故も、労山基金の交付対象とします。
交付申請には運営委員会から送付される所定の「事故確認書」の提出が必要です。
クライミングジムが管理している人工壁では、「事故確認書」を出してくれます。
管理されていない人工壁・プライベートの人工壁は、対象外になります。
なお、事前の山行計画書の写しは不要です。
A35.
結論から言うと登山の範疇ではないが、「会の企画として行なう会山行として、会員に等しく呼びかけて実施したもの」に限って認めています。
城跡・史跡巡り、神社・仏閣巡り、自然観察会などは登山とは異なるジャンルなので、交付の対象外としていました。これらはマウンテンバイクや洞窟探検と同様に、登山のジャンルと異なるスポーツのジャンルです。「登山口と下山口」が特定できないものであり、逆に定義することは困難です。
しかし、山を歩いていた人々が、麓を歩くようになり、これらはテーマ型ウォーキングとして人気があります。基金に対するアンケート結果から「高齢化に伴うテーマ型ウォーキングを労山基金の対象にしてほしい」との声が、全体の7割を占めるハイキングクラブから多数寄せられ、アルパインクラブは反対多数でした。この結果、基金運営委員会は「会員のニーズに応えるために、条件をつけて認める」ことにしました。個人山行ではなく「会主催企画」に限定されます。「会主催の企画」とは、複数の会員による運営委員会体制の下で、会行事として会員に周知された山行企画でこれ以外のウォーキング企画は対象となりません。
A36.
交通手段が自家用車と公共交通機関とでは対象範囲が異なる場合がありますが、車などを利用した登山への最終移動地から歩き出す地点を登山口とし、下山での最初の使用地点を下山口とします。
たとえば、富士吉田口から富士山を登る場合、富士急大月線の富士山駅から歩くときは、富士山駅が登山口、中の茶屋までタクシーで行き、そこから歩く場合は中の茶屋が、五合目のバス停まで行く場合は、五合目バス停が登山口になります。
また、登山道以外(車道等)を歩いて入・下山するとき、寄り道や登山活動以外の行為で怪我をした場合には対象外になります。
A37.
これまで、登山中に限定した怪我の入通院を想定した制度設計で、交付内容を維持してきました。会員の中心層が60台後半と高齢化が進むなかで、日常に潜む疾患が絡んで登山中の事故が発生したり、入通院の治療が長期化する傾向もあります。基金運営の健全性の維持と健康管理を踏まえた安全登山の啓発のために設けました。会や個人のレベルで「登山と健康、病気予防」をどうとらえていくか、また登山と疾病の関係での事故抑止を取り組むきっかけとして位置付けてもらいたいということが趣旨です。
A38.
運営委員会が作成した問診票などにより、これまでの療養等の経過を確認します。これに基づいて交付の適用を判断しますが、当面以下のようにガイドラインを設けて対応します。
(1) 登山中の発症や症状悪化の可能性などについて、特に医師から事前に指摘のない場合には適用しない。
(2) 日常の療養が医師の指示に基づいている場合においては適用しない。指示に反した場合に限る。
(3) 疾病の判断は、医師の診断書に基づく。
A39.
1件の事故につき、当該団体が救助活動以外の救援の要員を現地に派遣する場合について、交通費の限度額を示したものです。
要救援者の人数にはかかわりません。もし対象者が複数いた場合には、一件の費用を人数分で按分してください。
また、ココヘリ加入者の山岳遭難時において、ココヘリに「捜索要請」の連絡をした者が現地へ向かった場合は交通費を補助いたします。この場合の交通費1名分とし、交通費は遭難者の基金加入口数に応じて支払われます(1口につき1万円、最大10口10万円を上限とする)。
A40.
直接ココヘリに申し込んだ場合のケースですが、この場合もココヘリ加入の会員として同様に扱っています。労山基金の交付申請の時に、「ココヘリ加入済」と記入して提出いただくことが条件となります。